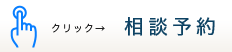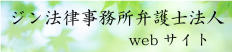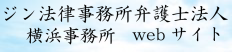FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.夫婦で同居義務を否定できる場合とは?
法的には夫婦には同居義務がありますが、これを拒否できる場合もあります。
同居義務の可否について、家庭裁判所と高等裁判所で判断が分かれたケースを紹介します。
離婚自体は否定されているものの、妻が適応障害、同居を拒否できるか争われた事案です。
動画での概略解説はこちら。
事案の概要
夫婦は、平成21年に婚姻。
夫の実家でその両親を含めて生活し、当事者双方の間に、平成24年長女Cが出生。
妻は、平成25年から、夫と別居し、当初は長女とともにその実家で生活していたが、後に肩書住所に長女とともに転居し、長女を監護養育。
夫は、実家でその両親とともに生活。
夫は、平成25年、妻との夫婦関係円満調整及び長女との面会交流を求める調停を申し立て、妻は、同年、夫との離婚を求める調停を申し立て、いずれも平成26年に不成立。
長女との面会交流を求める調停は審判に移行し、平成26年、夫が長女と少なくとも1か月に2回、午前10時から午後1時までの間面会交流し、長女の受渡場所をそのころ妻が居住していた妻の実家付近のコンビニエンスストアとするという審判がされ、確定。
妻は、平成26年離婚訴訟を提起。平成28年、離婚を認容する判決がされたが、夫が控訴を提起し、原判決を取り消して離婚請求を棄却する判決がされ、確定。
控訴審判決では、大要、妻と、同居していた夫の両親とのコミュニケーションの不全による妻のストレスはうかがわれるものの、夫のそれへの対応をとらえて妻への配慮に欠けたものとはいえず、別居後の夫に離婚に積極的な言動があったとはいえず、夫が妻及び長女に対する愛情を有し共に生活を営んでいくことを切望しており、婚姻関係が破綻しているとまでは認められないとの理由が述べられました。
夫は、平成28年、妻との同居を求める調停を申し立て、不成立。
家庭裁判所の判断
佐賀家庭裁判所審判平成29年3月29日は、同居を命じました。
「相手方は、申立人が、相手方及び当事者双方の長女Cのみが申立人と同居できる住居を、相手方が一般的な方法で通勤できる地域内に定めたときは、その住居において申立人と同居せよ。」との審判です。
一旦婚姻が成立すると、夫婦は同居し、互いに協力し扶助する義務が生じるところ(民法752条)、夫婦の同居は夫婦共同生活における本質的な義務であり、夫婦関係の実を挙げるために欠くことのできないものであるから、同居を拒否する正当な事由がない限り、夫婦の一方は他方に対し、同居を求めることができるとの論理を展開。
妻は、夫との離婚訴訟を提起して第1審で勝訴したものの控訴審でその判決が取り消されて請求を棄却されたのであるから、夫と同居する義務を負うことが確認され、控訴審の口頭弁論終結後に同居を拒否する正当な事由が生じたといえなければ、その義務は当然継続することになるとしています。
妻の症状と家裁の解釈
控訴審判決後も、妻は、離婚意思が固いとして、夫と直接接触せず、夫と長女との面会交流も、代理人弁護士事務所を通じて打ち合わせ、相手方の両親を介して長女の受け渡しを行うというものでした。
妻は、控訴審判決の前後を通じ、夫に関することを見聞きすると、蕁麻疹、吐き気、めまい、咳き込みなどを発症するので、夫と同居することは、妻に対し健康を害する環境で生活することを強要することであり、同居したくないのではなく、できないのであるなどと主張し、夫に対する嫌悪感や不信感があり、夫からの文書や手紙を見るだけで気分が悪くなり、夫との接触を考えただけで身体がかゆくなったり吐き気がしたりすると陳述し、ストレスなどによる慢性蕁麻疹と診断し、治療を必要とするとの内容の皮膚科医師作成の診断書に加え、適応障害(抑うつ状態)と診断し、ストレス因子は明確であり、治療には環境調整が必要と判断するとの内容の診断書も提出していました。
妻は、夫に対する嫌悪感の原因は、夫が、妻の説明や言い分を傾聴しないこと、存在しない事実を主張したり、事実を隠したり誇張して妻を非難すること、妻が主張してもいないことを勝手に想像し、その想像を前提に非難すること、自己の言動の矛盾を差し置いて妻を非難することなどであると主張していました。
妻は、同主張にかかる具体的事実の例として、平成28年に実施された長女の通う保育園の芋ほり行事に夫が参加を求めたことに関しての代理人弁護士事務所を通じてのやりとり、同年の長女との面会交流の際の長女の言動を巡っての代理人弁護士事務所を通じてのやりとりなどについての夫の子細な発言内容を、存在しない事実を主張したり、事実を隠したり誇張しているものとして非難するが、その主張にかかる具体的事実の内容を見ても、総じていえば、双方とも非常に批判的で疑心暗鬼であるうえ、代理人弁護士事務所を通じてやりとりをしているために、十分に意思疎通ができていないものであるということができると指摘。
そうすると、嫌悪感を抱く原因が、主として控訴審判決後の夫の妻に対する非難などの意図的な言動にあるとの妻の主張は、たやすく採用することはできないとしました。
妻の適応障害への対応は?
裁判所としては、妻の夫に対する拒絶が激しいので、まずは、家庭裁判所調査官を同席させたうえ、両者を面会させようとしたが、妻にその旨提案しただけで、手が震え呼吸が荒くなり嗚咽するという状況になったので、後日、家庭裁判所技官(医師)の受診をさせたところ、「元来健康、特記すべき家族歴や既往歴は無い方、現夫との物理的ないし心理的接近のたびに皮疹などの皮膚症状出現し、不安感も強まる。それ以外の際は、身体的な問題は起こらない状態である。精神医学的には『適応障害』と考えられる。ストレッサーと面会するためには抗不安薬の事前服用が必須と考えられ、その際でも精神症状の悪化は否定できない。」との診断がされました。
これに対し、妻は、投薬しても症状を回避できるかわからず、妻が安心して健康に生きることを否定するとして、家庭裁判所調査官を同席させたうえ抗不安薬を服用して夫と面会することは拒否しました。
妻は、控訴審判決後、長女と夫との面会交流には協力するものの、1度も夫と面接しようとはしていないと指摘。
控訴審判決により離婚請求を棄却された以上、原則として夫と同居する義務を負うにもかかわらず、その義務が履行できないことについて、夫に説明し謝罪する試みがされたとはうかがえないとしいています。
直接行うことができないとしても、妻には、代理人弁護士事務所を通じて連絡をする手段があるのに、それを利用しようとした形跡もないとも指摘。
妻が適応障害であるとの診断がされ、夫との物理的ないし心理的接近のたびに皮膚症状や不安感が生じるとしても、奏効するかどうかはともかく、面会に先立ち抗不安薬を服用するという手段が示唆されているところであるとしています。
以上のとおり、妻は、控訴審判決後、夫との同居のための第1歩となる夫との面会、そのきっかけとなるべき書面や手紙での夫との交流なども一切試みようとしていないので、夫との物理的ないし心理的接近をストレッサーとする適応障害であるとの診断があるだけでは、いまだ同居を拒否する正当な事由が生じているとはいえないとしました。
同居を命じる場合の具体的な内容
ところで、夫婦同居の審判は、その実体的権利義務自体を確定するというよりは、それがあることを前提として、その具体的内容を定めるものであるというべきであるとしています。
そこで、夫と妻の生活状況を検討すると、妻は長女と肩書住所で生活し、夫はその実家で両親と生活していると認定。
妻が夫との離婚を求める理由に、夫の両親との不和を挙げており、控訴審判決でもその事情自体は一定程度認定されているから、妻に夫の実家での同居を命じるのは相当でないとしました。
夫は、妻住所での同居を求めるようであるが、その住居が長女を含め3名で居住するに相応しいとの証拠がないばかりか、同居義務が強制履行を求めることのできないものである以上、夫が妻の承諾なく妻住居に立ち入ることを許容するとは考え難く、そのような行為を許容するかの誤解を与えかねない妻住所での同居という内容は相当とはいえないとしました。
現実に、妻と夫との同居が実現するためには、まずは、例えば、書面での交流などの間接的な方法から始めて、第三者を交えるなどして直接面会をする機会を作り、さらに当事者のみで面会する機会につなげていくなどの手順を踏むことが考えられるが、その過程を審判で定めることはできないので、結局は、抽象的であれ、そのような過程を経て考えられる同居形態を定めるしかないとしました。
これにより主文のような判断がされたものです。
「相手方は、申立人が、相手方及び当事者双方の長女Cのみが申立人と同居できる住居を、相手方が一般的な方法で通勤できる地域内に定めたときは、その住居において申立人と同居せよ。」
同居を命じる審判例として参考になるかと思います。
ただし、本件については、高裁で判断が覆っています。
高等裁判所の判断
福岡高等裁判所平成29年7月14日決定は、同居を否定しました。
原審判を取り消し、申立てを却下するとの結論です。
妻の抗告理由は次のようなものでした。
婚姻関係が破綻状態にある場合、同居拒否の正当事由があるというべきところ、この場合の破綻状態は、離婚事由である婚姻を継続し難い重大な事由とされるものと同程度のものである必要はないとの主張。
したがって、離婚訴訟で離婚が認められなかったからといって、その時点で、当然に同居拒否の正当事由までもが存在しなかったということにはならないとの論理です。そうすると、正当事由の有無については、別居に至る経緯も踏まえて判断すべきであるのに、原審判は、離婚判決後に婚姻関係が破綻したかどうかという視点のみからしか正当事由の有無を検討しておらず、不当であると主張。
妻は、原審において、家庭裁判所調査官らの立会いの下での夫との面会を試みようとしただけも身体に不調を来しており、家庭裁判所技官によって、相手方をストレッサーとする適応障害と診断されているとの主張。
夫はこれらの点を争っています。
同居義務とは?
高等裁判所は、夫婦である以上、一般的、抽象的な意味における同居義務を負っている(民法752条)と前提を確認。
しかしながら、この意味における同居義務があるからといって、婚姻が継続する限り同居を拒み得ないと解するのは相当でなく、その具体的な義務の内容(同居の時期、場所、態様等)については、夫婦間で合意ができない場合には家庭裁判所が審判によって同居の当否を審理した上で、同居が相当と認められる場合に、個別的、具体的に形成されるべきものであるとしました。
そうであるとすれば、当該事案における具体的な事情の下において、同居義務の具体的内容を形成することが不相当と認められる場合には、家庭裁判所は、その裁量権に基づき同居義務の具体的内容の形成を拒否することができるというべきであるとしています。
そして、同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであることからすると、共同生活を営む夫婦間の愛情と信頼関係が失われる等した結果、仮に、同居の審判がされて、同居生活が再開されたとしても、夫婦が互いの人格を傷つけ、又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には、同居を命じるのは相当ではないといえるとしました。
夫婦関係の破綻の程度が、離婚原因の程度に至らなくても、同居義務の具体的形成をすることが不相当な場合はあり得ると解されるとしています。離婚の判断と、同居の判断基準は異なるというロジックです。
同居と適応障害の考慮
本件において、もともと妻が夫との別居を開始したのは、夫の両親との不和に原因があったものと思われるが、その後、夫との話合いが繰り返される中で、その内容が、夫実家での同居、別の場所での同居、離婚といった経緯をたどるうち、上記離婚訴訟の判決に至るまでの間に、妻の夫に対する不信感、嫌悪感が強まっていき、現時点で、妻は、適応障害の症状を呈しており、そのストレッサーとされるのが夫であることは明らかであると認めました。
この点、夫は、自身はストレッサーではなく、夫との紛争状態こそが妻のストレス原因であると主張していました。しかしながら、妻について、調停において夫と同席した際にのみ身体症状が現れていることなども踏まえると、紛争状態の継続が妻の適応障害の背景にあることは否定できないとしても、ストレッサーとなっているのは、夫自身あるいは夫との関わりであるというべきであるとしました。
また、夫が作成している書面の内容からは、夫において、面会交流のあり方を含めた長女との交流について強いこだわりを有していること、それが、長女を監護している妻との同居を求める大きな動機になっている様子はうかがわれるものの、妻自身の体調などに対する労りといった心情などはうかがわれず、夫が、妻から嫌悪されていることを自覚している様子がうかがわれると指摘。
かかる事情を踏まえると、妻について、あらかじめ薬を服用することで適応障害の症状を抑えることができる可能性はあるとしても、そのようにしてまで夫との同居生活を再開したところで、妻において、早晩、服薬によって症状を抑えることも困難となり、再度別居せざるを得なくなる可能性は高いということができ、上記夫の作成した書面の内容や、これまで当事者双方が互いに批判的で疑心暗鬼の状態にあることに照らすと、そのような事態に至った時に、夫から妻に対し、適切な配慮がされるとは思われず、相互に個人の尊厳を損なうような状態に至る可能性は高いといわざるを得ないとしました。
離婚請求の棄却判決の解釈
本件においては、妻が提起した離婚訴訟において、いまだ婚姻を継続し難い重大な事由があるとまでは認められないとして請求を棄却する判決が平成28年に確定しているものの、控訴審判決は上記の別居期間が、妻と夫において共に生活を営んでいくのが客観的に困難になるほどの長期に及んだものとはいえないとし、婚姻関係の修復の可能性がないとまではいえないことから離婚請求を棄却したにとどまるものであって、抗婚姻関係は、上記判決の時点でも既に修復を要するような状態にあったことは、明らかであると指摘。
控訴審における弁論終結の時点で、婚姻期間中の同居期間が約3年10か月であるのに対し、別居期間は約2年7か月に及んでおり、その後、妻の夫に対する不信感等は、夫自身をストレッサーとして適応障害の症状を呈するほどに高まっていると認定。
そうすると、夫婦関係の破綻の程度は、離婚原因といえる程度に至っていないとしても、同居義務の具体的形成をすることが不相当な程度には至っていたというべきであるとしました。
条件付きであっても、やはり現時点で、同居を命じるのは相当ではないとしました。
同居義務に関する審判例
同居義務については、同居拒否の正当事由があるかどうかを問題にする裁判例、諸般の事情から同居を命じることが個人の尊厳を損なうかどうかなどを問題にする裁判例があります。
婚姻破綻の程度については、同居を命じるかの判断要素とされます。
ただ、その程度に関しては、離婚事由で求められる程度とは違うとされました。
本件では、そのほかに、適応障害の点が考慮されたものと思われます。
別居を含めた離婚のご相談は、以下のボタンよりお申し込みください。