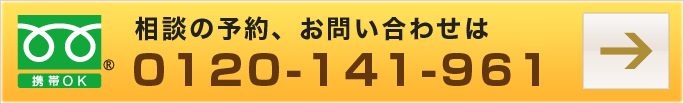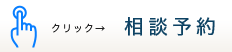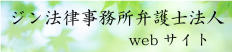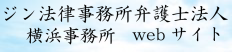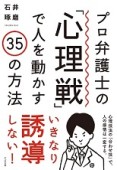FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.養育費変更と借金の関係は?
養育費の合意は絶対ではありません。東京高裁令和6年11月21日決定は、月2万円から3万1000円への増額を認め、離婚後の事情変更があれば裁判所が合意を変更できることを示しました。
借金完済や収入変動など複数の変化を考慮し、改定標準算定方式で公平な額を算出。
離婚後の個人的借金は減額理由にならず、増額開始時期は請求時ではなく条件が揃った時点からと判断されました。
養育費変更を検討中の方はチェックしておくべき内容でしょう。
重要なチェックポイントから紹介します。
この記事をチェックすると良い人は、次のような人。
- ・養育費の増額または減額を検討している元配偶者
- ・収入変動や生活状況の変化により養育費の見直しが必要な人
ポイント1:当事者間の「合意」も、裁判所は変更できる
離婚時に元夫婦が養育費の金額について話し合い、月2万円で合意していたとしても、それは永遠に固定されるわけではありません。
今回のケースで最も重要なのは、合意後に「事情の変更(事情変更)」があった場合、裁判所はその合意内容を変更できるという点です。
このケースでは、合意後に以下のような複数の変化がありました。
1. 父親が、離婚前から抱えていた借金を完済したこと
2. 父親が、別の女性との間に第三子をもうけたこと
3. 母親が、就労状態から傷病手当を受給する状態に変わったこと
4. 父親の仕事が変わり、収入が大きく変動したこと
裁判所は、これらの変化を踏まえ、まず現在の状況で「本来あるべき養育費の額」を算出しました。
その際に用いるのが「改定標準算定方式」という、裁判所が使う公式の計算式です。
これは、両親の収入などをもとに公平な養育費を割り出すためのもので、この計算の結果、月額3万1000円という金額が導き出されました。
当初合意した月額2万円と、現在の状況で算出した月額3万1000円とでは「大きく異なる」ため、裁判所は「当初の合意はもはや現在の実情に適合せず、相当性を欠く」と判断。
つまり、過去の合意の継続が不公平な状態を生むとみなし、変更を命じたのです。
裁判所は、この点について以下のように明確に述べています。
家庭裁判所は、養育費の額について協議がされた場合であっても、協議の際に基礎とされた事情に変更が生じた結果、協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、協議の内容を変更することができる
これは、当事者の合意よりも「子の福祉」を優先するという、家庭裁判所の基本的な姿勢を示すものです。
ポイント2:「離婚後の借金」は養育費を減らす理由にならない
この裁判で、父親側は自身の新たな借金を理由に、養育費の増額に反対しました。

しかし、裁判所の判断は非常に明確でした。
まず、離婚時に存在した約100万円の消費者金融からの借金は、もともと「夫婦の生活費等のために作られた可能性がある」として、当初の養育費を月2万円とする際に考慮されていました。
そして、この借金を完済したこと自体が、父親の支払い能力が上がった「事情変更」の一つとして、養育費を増額する根拠とされたのです。
これに対し、父親が離婚後に新たに作った借金については、裁判所は全く異なる見方をしました。
その借金は、元妻とは無関係に、父親個人の事情で作られたものです。
裁判所は、元妻が「返済の負担を分かち合うべき事情はない」と指摘し、それを理由に子どもへの養育費を減額することは認められない、と一蹴しました。
これは、家族のために生じた負債と、家族が解消された後に個人が作った負債とを明確に区別するという、非常に重要な法的原則を示しています。
親自身の経済的な選択が、子どもの権利である養育費を侵害してはならないという強いメッセージと言えるでしょう。
裁判所のこの断固たる姿勢は、以下の言葉に集約されています。
「抗告人が相手方との離婚後にした借入れについては、抗告人と相手方が返済の負担を分ち合うべき事情はなく、抗告人が分担すべき未成年者の養育費の額を定めるに当たって、これを考慮することが相当であるとはいえない。」
ポイント3:増額の開始時期は「請求した日」とは限らない
通常、養育費の増額を求める場合、その増額分は「増額を求める調停を申し立てた月」から発生すると考えられがちです。このケースでは、母親が申し立てをしたのは令和4年9月でした。
しかし、高等裁判所は増額の開始時期をそれより後の「令和4年12月」と定めたのです。
なぜでしょうか?
その理由は、裁判所が「増額を正当化するすべての事情変更が揃った時点」を開始時期とすべきだと考えたからです。
法的に見ると、申し立てがあった9月の時点では、まだ増額を認める条件が完全には整っていませんでした。
というのも、その時点での父親の収入は月10万円程度と、まだ低かったのです。
しかし、同年12月から父親は会社員として月収32万円の安定した高収入を得るようになりました。
この瞬間に初めて、増額を正当化する「父親の支払い能力の向上」という最後のピースがはまったのです。
つまり、裁判所は単に「公平だから」という理由で日付を選んだのではなく、「増額の法的根拠が完全に成立した瞬間」を正確に特定したのです。
これは、請求したからといってすぐに増額が認められるわけではなく、双方の状況が整った最も妥当な時期が判断されることを示しています。
全体としては、基本は請求時だが、実は請求時には事情変更がなかった場合には、変更時期という判断のように読めます。
養育費事案の概要
ここからは、全体に東京高等裁判所令和6年11月21日決定の内容を見ていきます。
本件は、協議離婚時に月額2万円の養育費で合意した元夫婦間において、親権者である母(相手方)が、子を監護していない父(抗告人)に対し養育費の増額を求めた事案です。
・当初の合意内容
「未成年者が満20歳に達する月まで、毎月2万円を支払う。」
合意の性質は、私的合意で、債務名義とはなっていません。
請求内容は、相手方(母)が養育費増額を求める調停を申し立て(令和4年9月)。
原審(横浜家裁小田原支部)の判断
横浜家庭裁判所小田原支部は、令和5年8月10日の審判において、以下の判断を下しました。
• 合意の扱い: 本件合意が債務名義になっていないことを理由に、合意の「変更」ではなく、一般の養育費申立事件として新たに養育費分担額を定めるのが相当と判断。
• 算定: 改定標準算定方式に基づき、抗告人が支払うべき養育費を月額3万2000円と算定。
• 支払命令: 支払始期を調停申立月の令和4年9月とし、過去分35万2000円(11か月分)と、将来分として月額3万2000円の支払いを命じました。
東京高等裁判所の判断
抗告人(父)が原審判を不服として抗告。
東京高等裁判所は令和6年11月21日の決定で原審判を変更し、以下の通り結論付けました。
• 合意の扱い: 原審とは異なり、本件合意を基礎としつつ、「事情の変更」を理由として合意内容を変更するのが相当と判断。
• 算定: 改定標準算定方式による試算額を基に、変更後の養育費を月額3万1000円と決定。
• 支払命令: 支払始期を、後述する事情変更が全て生じた令和4年12月とし、過去分71万3000円(23か月分)と、将来分として月額3万1000円の支払いを命じました。
「事情変更の原則」の適用
本件における最大の争点は、一度当事者間で合意した養育費の額を、裁判所が事後的に変更できるか、またその要件は何かという点でした。
東京高裁は、民法880条を根拠に、「家庭裁判所は、養育費の額について協議がされた場合であっても、協議の際に基礎とされた事情に変更が生じた結果、協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、協議の内容を変更することができる」と判示。
これは、従来の判例と同様の考え方です。
「これを本件についてみると、本件合意の後、①抗告人による本件借入れの返済、②第3子の誕生、③相手方の就労・傷病手当の受給、④抗告人の稼働状況の変化といった事情の変更が生じたと認められる。したがって、これらの事情の変更によって本件合意の定める養育費の額が実情に適合せず、相当性を欠くに至った場合には、家庭裁判所は、本件合意によって定められ養育費の額を変更することができる。」
事情変更の評価手法
高裁は、これらの事情変更が「協議の内容を実情に適合させず、相当性を欠く」レベルに至ったかを判断するため、特徴的な手法を採用。
1. まず、上記の変更後の事情を前提として、「仮に改定標準算定方式を適用した場合に抗告人が分担すべきことになる未成年者の養育費の額」を試算。
2. 次に、その試算結果(月額3万1000円)が、「本件合意によって定められた養育費の額(月額2万円)と大きく異なる」かを評価。
3. 本件では1.55倍の差があり「大きく異なる」と判断し、これにより「本件合意によって定められた養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至った」と結論付けています。
この手法について、「当事者が改定標準算定方式に基づいて養育費の額を定めたことを事実上推定するもの」とする解説もあります。
基礎収入の認定
• 相手方(母)の収入:
◦ 調停申立時の傷病手当(年額156万円)を総収入とする。
◦ 傷病手当の受給に職業費は不要である点を考慮し、給与収入に換算(183万5294円)。
◦ 換算後の収入に基づき、基礎収入を78万9176円と算定した(高裁)。
• 抗告人(父)の収入:
◦ 令和4年12月以降の月額32万円の給与収入を基に、年収を384万円と認定。
◦ 基礎収入を161万2800円と算定した(高裁)。
• 収入不明な者の収入推計(原審):
◦ 抗告人(父): 期日に出頭せず収入資料も提出しなかったため、申立人(母)の陳述に基づき、同居時の収入(月額27万5000円)程度の稼働能力があると認め、総収入を330万円と推認した。
◦ 第1子の父: 収入不明のため、「令和4年賃金構造基本統計調査」に基づき、中学卒・25~29歳男性の平均賃金から総収入を371万円と推計。
まとめ
今回の裁判例は、養育費をめぐる法律が非常に動的であることを教えてくれます。
ポイントをまとめると、以下のようになります。
1. 過去の合意は絶対ではない:生活状況が大きく変われば、合意は見直されるべき(ポイント1)。
2. 子の権利は親の都合に優先する:離婚後の個人的な借金は、養育費を減額する正当な理由にならない(ポイント2)。
3. 法的根拠の成立時期が重要:増額の開始は、請求日ではなく、増額を正当化する条件がすべて揃った時点からと判断されることがある(ポイント3)。
事情変更による養育費の変更を主張したい人は参考にしてみてください。
離婚に関するご相談(面談)は、以下のボタンよりお申し込みください。